こんにちは。
7月に入り「お中元」の時期になりましたね。
「お中元」が、届くととてもうれしい気持ちになりますが、
- 「お中元をもらったらお返しはいいのかしら?」
- 「お中元を贈らいたい時はどんなことに気をつけないといけないの?」
- 「そもそもお中元って、何のために贈ったり、贈られたりするの?」
案外お中元についてあいまいなことってありませんか?
ここでは、お中元の起源やお中元のマナー、どんなお中元が喜ばれるかこの際、お中元についてしっかり学んでおきましょう。
ここでは、お中元の起源やお中元の意味についてお話します。
お中元とは

お中元の起源は中国に在ります。
1336~1573年、日本が室町時代にお中元の文化が中国より入ってきたと言われています。
中国には儒教や道教などの中国独自宗教がありますが、お中元は「道教」と結びついています。道教には「三元」の祭日がありそれぞれあります。
- 上元:旧暦1月15日
- 中元:旧暦7月15日
- 下元:旧暦10月15日
旧暦は月の満ち欠けを基準としており、新暦は地球が太陽の周りをまわる周期を基準にした年号です。
よって新暦はおよそ1か月、旧暦より季節が早くなりますので、新暦だと下記のようになります。
- 上元:新暦2月15日
- 中元:新暦8月15日
- 下元:新暦11月15日
という具合になり、「中元」は7月15日~8月15日くらいの期間にあたり、「中元」だけが日本の風習「お盆」と結びついて入り、定着していったものです。
道教はもともと「多神教」という特徴があり、八百万神を信仰する日本の宗教、新道(しんどう)と相性が良いこともあったのではないかと言われています。
江戸時代から定着
室町時代から入ってきたこちらの風習は、江戸時代になって定着してきました。
また年末に贈り物をする風習「お歳暮」もまた江戸時代です。
神様へのお供え物として、お餅・お米・お酒などを送っていたのが、ともに人々も食べることで、神様と一緒に食事をする特別な目的として始まったと、民俗学者の柳田国男が説を唱えています。
年中行事として継続していくにつれ、そうして宗教的な考えが薄れ「お世話になった人への感謝の気持ち」という意味に移り変わっていったようです。
【参考サイト】
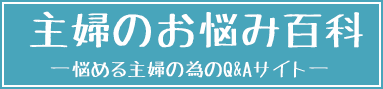
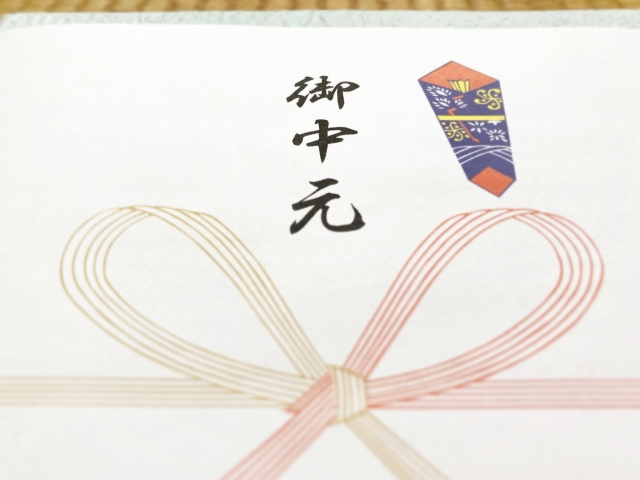

 回覧板の回し方が分からない
回覧板の回し方が分からない  英会話勉強用にパソコンを購入しに行く
英会話勉強用にパソコンを購入しに行く  隣人に通行料を請求された
隣人に通行料を請求された  姑より小姑と相性が合わない
姑より小姑と相性が合わない