予防接種は「定期接種」と「任意接種」の2タイプ
子供に予防接種を受けさせるには、各親が責任を持って判断したうえで受けさせなくてはいけません。
予防接種は定期と任意の2種類あり、定期は国が定める年令になれば、受けるよう務める旨が定められており、強い感染力を持ち、公共性の面から見ても予防の必然性が高いと認められます。
定められた期間内であれば無料で接種できるのが一般的ですが、自治体により有料扱いの場合もあります。
もしも、この予防接種により重い副作用が発現した場合は、接種と副作用の因果関係が認定されれば国からの保障を受けることが可能です。
これに対し、任意接種は、親が希望する場合に個別に病院やクリニックで接種するもので、基本的にはその費用は自己負担なのですが、自治体により補助金が出て一部負担等ですむ場合もあります。
任意ですが、こどもがもしその病気にかかって重症化するリスクを考慮すれば、予め受けておいた方が安心です。
しかし、とりあえず全部受けるということが良いのかどうかは迷うところです。
それは任意の予防接種を受けて重症化せずに済んだというケースもあれば、ときおり裁判に発展しているように、予防接種の副作用で好ましくない後遺症が出るケースがあるからです。
任意予防接種の副作用・副反応の多くは軽度
両親が希望して受けさせる予防接種は任意なので自治体等からのお知らせ・案内はありません。
ワクチンの種類は水疱瘡、おたふくかぜ、A・B型の肝炎などがあり、これらの中には成人になって発症すれば重篤化するケースがあるので接種が望まれます。
接種方法は個別に病院を訪れて接種しますが、この副作用あるいは副反応と言われるものの多くは、「カユミ」「発熱」「赤み」「腫れる」といった症状であることが多いです。
それらの反応は体内に異物が侵入した際に起きる反応で、微弱であれば感じないこともあります。
多くの場合は反応が出ても数日から10日程度で収まります。
予防接種後に必要な観察
予防接種を受けた当日から2~3日間は手足を動かしづらそうにしていないか、顔色が悪くなったり唇が紫色に変化したりしていないか、ぐったりした様子ではないか、嘔吐や血便などの異常は無いかの観察が大事です。
その後も発熱や嘔吐を含め異常はないかの観察を続けます。
異常の兆候があれば、早めに診察を受けるようにします。
予防接種の前後の過ごし方
予防接種は出来るだけ体調の良い時に受けるように心がけます。
予防接種による重度の副反応は、接種後おおむね30分程度で症状があらわれると言われます。
ですので、接種後30分は異常があればすぐに医師の診察が受けられるよう、病院内に滞在することが望まれます。
その後も激しい運動は避け、接種した場所を刺激しないよう気を付けます。
あくまでも予防接種を受けるか否かの判断は両親の責任ですので、十分情報を集めてから判断しましょう。
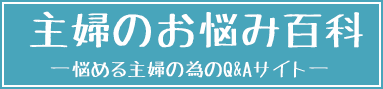


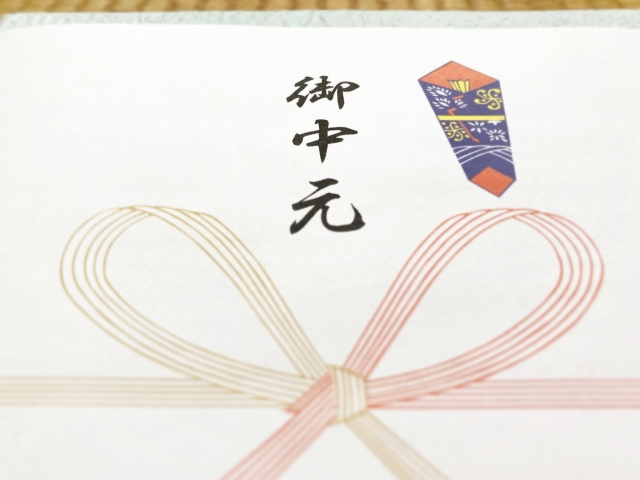 お中元の起源
お中元の起源  回覧板の回し方が分からない
回覧板の回し方が分からない  英会話勉強用にパソコンを購入しに行く
英会話勉強用にパソコンを購入しに行く  隣人に通行料を請求された
隣人に通行料を請求された  姑より小姑と相性が合わない
姑より小姑と相性が合わない