不登校数は再び微増中
小中学校における不登校数は平成元年から約10年間の間に急激に上昇してきました。
以前からも学校にいけない子供はたくさんいましたが、学校内の問題として世間的に可視化されることはありませんでした。
しかしその数が平成10年までに急増をしたことから、文部科学省でも本格的な調査と対策をとるようになりました。
その成果もあり小中学校全体での不登校児童数は平成13年ころから微減傾向が見られるようになっています。
しかし平成19年ころから再び上昇傾向に転じており、そのあともう一度下降はしたものの現在は再び上昇に転じる傾向が見られています。
ない文部科学省が「不登校」と定める条件は年間30日以上欠席をした子供のことで、2013年度の数値では小中学校合わせて約12万人がそれに当てはまっていることがわかっています。
子供の不登校の原因というのは大人が完全に把握することは難しく、子供同士の人間関係だけでなく本人の無気力や非行、学業不振といったいくつかの要因が重なり合ってできあがっています。
大人としては子供が学校に行きたくないと言い出した時には「きっと学校で誰かにいじめられているに違いない」と学校に意見をしに行きたくなるところですが、実際にはとくにひどいいじめの実態はなく担任や先生たちにとってもどう対応してよいかわからないということも多いのが実態です。
親自身が子供の不登校の原因になっていることもあります
まず最初にしっかり理解しておいてもらいたいのが、子供の不登校の原因は決して一つではないということです。
先ほど原因は複数の要因が重なってできると言いましたが、そこにさらに子供の家庭問題が関係しているということもあります。
子供が不登校になってしまったとき、真面目な親ほどまず自分たちを「教育の仕方が悪かったのかも」と責め、さらに「学校がきちんと子供のことを見てくれないのが悪い」と周囲を責めます。
確かに学校が特定の子供に対してえこひいきや厳しい態度をとるということはないわけではありませんが、現在学校の先生として勤務されている人の多くはきちんと自分の仕事をされています。
子供が不登校になったときに、大人が大人を責めてもそれが解決になるということはまずほとんどありません。
大切なのは子供の気持ちにしっかり寄り添い、一体どういったことが学校に行きたいという気持ちを阻害しているのかということをゆっくり解きほぐしていくということです。
それは時に時間がかかってしまうこともありますが、焦らず子供のペースに合わせてあげるようにするということが初期対応としては重要です。
「嫌な事から逃げる」ことだけは禁止
しかし親にしてみると、子供が不登校になってしまうとどうしても「このまま中年になるまでずっと引きこもりになったらどうしよう」といった将来の不安を感じたりもします。
実際中高年の引きこもりは現在社会問題になっており、引きこもりの期間が長くなるほどますます社会に出ていきにくくなってしまうという現状もあります。
ですが不登校の原因が学校内でのトラブルや思春期の悩みである場合には、本人も「このままではいけない」という意識を持っているので時間が解決をしてくれることもあります。
問題は精神的が未成熟なことにより、甘えから学校に行きたくないという態度をとってしまった場合です。
子供の様子を見て何が原因であるか、地域のカウンセラーなどに相談しながら判断していき、長期化をしないように学校以外の施設に通わせるなど少しずつ現実生活に適応させていくようにしましょう。
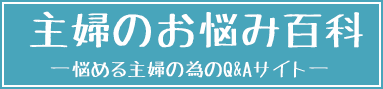


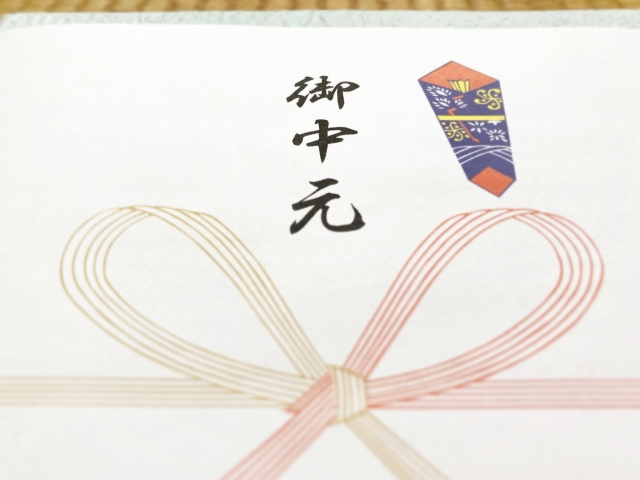 お中元の起源
お中元の起源  回覧板の回し方が分からない
回覧板の回し方が分からない  英会話勉強用にパソコンを購入しに行く
英会話勉強用にパソコンを購入しに行く  隣人に通行料を請求された
隣人に通行料を請求された  姑より小姑と相性が合わない
姑より小姑と相性が合わない