七五三の年齢
子供の成長を祝う定例の行事の代表格として、七五三が挙げられます。
子供が三才・五才・七才に近づいたら忘れずに準備をしてあげましょう。
七五三は子供の健康で元気な成長を祝い今後とも障りなく育ってほしいと願って行う日本に古来より伝わる伝統的な行事です。
基本的には、男の子は三才・五才、女の子は三才・七才が対象とされていますが、一部省略するケースもあります。
従来は数え年(かぞえどし)が用いられ、この年令の数え方は、生まれた年を1才と捉える考え方です。
つまり、生まれた年に既に1才であり、年の初めの元日を迎えるたびに1才ずつ年令を重ねていくことになります。
ネズミ年に生まれた人は年が変わって翌丑年の正月を迎えるとみんな一緒に2才になるのです。
極端な例で言えば、12月31日に生まれた人は、翌日正月には2歳となるのです。
これに対し、誕生日の前日の24時を経過したときに1才加える年令の数え方を満年齢といい、現在ではこの方法で数えて七五三の年令を計算する方も増えています。
この行事は、元々関東地方で古くから行われていた地方風俗でした。
この時代は乳幼児の死亡率が高く、3才を無事に元気に迎えることは家族にとって大きな喜びで祝い事とされたのです。
また、3才になると言語の認識が始まり、5才で知識が付き始め、7才で永久歯が生え始まるという、子供の成長の身体・精神的な成長の節目であっために、この年令が選ばれ、各地方に広まりました。
具体的なイベント
現在のイベントは時代とともに少しずつ変化し、また地方や家庭でも差異はありますが、共通するのは、近くの有名な神社に参拝し、お祓いなどをしてもらいます。
そのあとは、写真館で写真を撮ることが多いのですが、近年では七五三のシーズンが込み合い予約も取りにくいため、事前に和服の着付けをして写真撮影を済ませる方も増えています。
また、神社に参拝した後は、家族そろってレストランやホテルで食事をしたりします。
七五三のお参りをする日
七五三のお参りは、11月15日に行う行事とされていましたが、それは旧暦で15日は、「28宿の鬼宿日」と言われ、鬼が出歩かない日とされていたからです。
婚礼を除き、すべてにおいて吉の日だったのです。
また、旧暦で11月は、秋の農作物の収穫を終える時期で作業は一段落し、秋祭りの多くは豊作を神に感謝する行事でした。
そこで11月の15日に、神へ豊作と子供の健康に感謝し、今後も元気に成長するよう神のご加護を祈る行事として七五三が始められたと言われます。
現在では必ずしもこの日に行わない方も多く10月中旬から11月下旬にかけて大安や先勝など縁起の良いとされる日や家族の日程が確保できる日に行う家庭が増えています。
しかし、地方により慣習が異なりますので、親戚や地域の知人、参拝しようと思っている神社に確認すると有益な情報が得やすいと思われます。
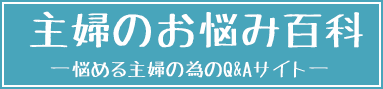


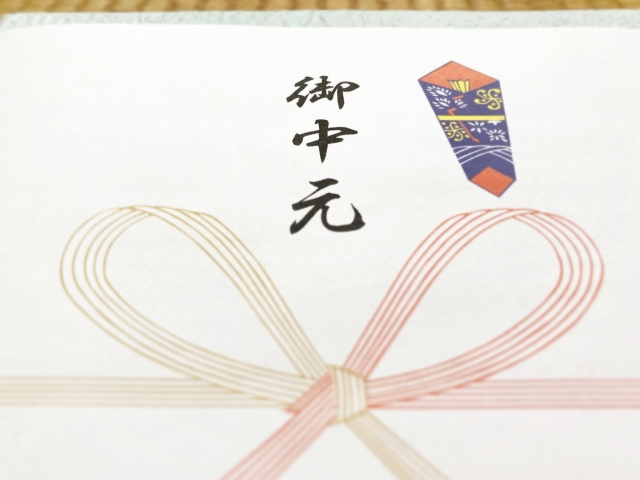 お中元の起源
お中元の起源  回覧板の回し方が分からない
回覧板の回し方が分からない  英会話勉強用にパソコンを購入しに行く
英会話勉強用にパソコンを購入しに行く  隣人に通行料を請求された
隣人に通行料を請求された  姑より小姑と相性が合わない
姑より小姑と相性が合わない