「言ってもやらない」という子供への対応方法
親としては子供にはいつまでも自分に甘えてほしいと思う一方で、早く自立した生活ができるようになってほしいとも思ってしまうものです。
子供も幼稚園や保育園に入園するくらいの時期になると、一人で着替えをしたり部屋のお片づけをしたりといったことができるようになります。
そこで親も朝や夕方の忙しい時間帯には「早く○○して!」といった指示を出したりするものですが、その気持ちに反して言われてもすぐに動かない子供もよくいます。
着替えや片付けくらいなら多少遅れてもあとでやってくれればよいのですが、それが小学校に入学して勉強をするようになるとやる気の有無がそのまま成績に反映されてきてしまいます。
毎回悪い点数をテストでとってくる子供を見ると、親としては「どうして勉強しないの!」と怒りたくもなってしまいます。
しかしそうして怒ったり急かしたりすればするほど子供はやる気をなくし、やっても渋々といった感じで自分の身にならないやり方をとってしまいます。
子供のしつけで大切なのは「無理やりやらせる」のではなくできるだけ「自分の意志でする」ように気持ちを持たせるということです。
運動量そのものが足りないのではありませんか?
大人の感覚では「運動ができる」と「頭が良い」はまったく異なる才能のように思います。
ですが子供時代、特に幼い時期というのは頭の良さと運動量はかなり近い相関関係があります。
大人でもストレスがたまったときに思い切り体を動かすと頭がすっきりするということがありますが、体が活発に動くことで脳にもよい影響が及ぼされるのです。
一般的な傾向としてやる気がない子供というのは全体的な運動量が足りていないことがよくあります。
散歩でもスポーツでも何でもよいので、できるだけ普段から体を多く使うようにしてあげることで一日のうちの活動量が増え頭の回転も速くなります。
子供時代というのは高校生や大学生のように特定の勉強だけをさせてもそれほど学力を伸ばすことはできません。
むしろ小さいうちは思い切り体を動かしながら脳の使い方を広げるようにしていくことが、のちの勉強意欲や効率を高めるとまで言われています。
ですのでまずはいきなりさせたいことを命令するのではく、ゴロゴロしているだけの生活をやめて体を一緒に動かせるような習慣を作っていきましょう。
小さなことからさせてみる
子供が言われたことをすぐしないときによくあるのが「作業量が多くてどれからすればよいのかわからない」ということです。
例えば部屋の片づけ一つにしても部屋全体が散らかっているとどこからどう片付けていいかがわかりませんので、単純に「片付けなさい」と言われても面倒くさくなってそのままにしてしまいます。
ですのでそうしたときにはまず親としては「まずこのブロックを箱の中に入れて」「ぬいぐるみを棚に置いて」といったように一つの作業ごとに丁寧に指示していきましょう。
勉強においても同じで、ただ「宿題しなさい」と言うのではなく「漢字の書き取りをして」といったように具体的な作業を指示することで子供の腰を上げさせることができます。
私たちもよく仕事などで100枚の書類を書けと思うと大変なので、「今日は10枚だけ書こう」というふうに目の前の作業を具体化させることでモチベーションを上げたりします。
もちろんできる子供に細かく指示する必要はありませんが、もし言ってもやらないことに悩んでいるならそうした小目標の設定から試してみてください。
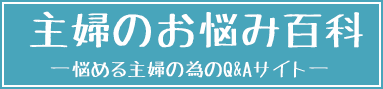


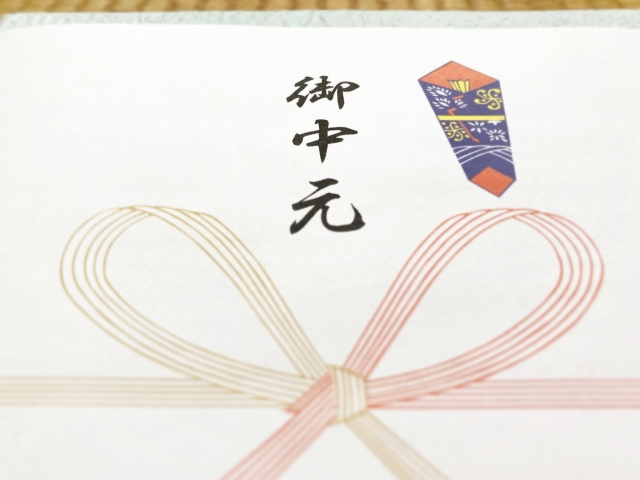 お中元の起源
お中元の起源  回覧板の回し方が分からない
回覧板の回し方が分からない  英会話勉強用にパソコンを購入しに行く
英会話勉強用にパソコンを購入しに行く  隣人に通行料を請求された
隣人に通行料を請求された  姑より小姑と相性が合わない
姑より小姑と相性が合わない