子どもの自転車デビューは何歳からがいいのでしょうか。
子どもは大きくなるにつれて自転車に興味を持ち始めます。ペダルのないストライダーのようなキックバイクの普及によって補助輪なしで自転車に乗る時期は低年齢化しています。
しかし乗りこなせずケガをしてしまうかもしれませんし、小さな自転車でもスピードが出せるのは危険ですよね。子どもには安全に遊んでほしいものです。
そこで今回は子どもの自転車デビューの年齢や練習方法、自転車の選び方などについて紹介します。
自転車デビューは何歳から?
子どもの補助輪なしの自転車デビューは低年齢化しています。
2018年にトイザらスが20歳以上の人が自転車に乗れるようになった年齢を調査した結果によると、平均年齢は5.7歳でした。
これに対し、回答者の子どもが自転車に乗れた平均年齢は4.9歳と、0.8歳の差があったのです。
ストライダーが普及したほか、幼児用自転車のサイズ幅が広がったことにより、低年齢から自転車に乗る練習がしやすくなった背景があるとみられています。
ストライダーとは、ペダルやブレーキのない自転車型の乗り物です。ハンドルを持ちサドルにまたがり、足で地面を蹴って進みます。1歳半から乗れるため、ストライダーを通して自転車デビューできるわけです。
補助輪なしで乗れるのは何歳から?
子どもが補助輪なしの自転車に乗れるようになるのは平均年齢4.9歳であることから、5歳前後が目安です。
6歳までにはほとんどの子どもが自転車に乗れるようになっていると思っていいでしょう。
これは自転車のチャイルドシートに子どもを乗せられるのは6歳未満(小学校入学前)までと、法律で決まっていることも影響していると考えられます。
子ども用自転車の選び方
子ども用自転車のサイズについて
子ども用自転車には色々なサイズがあり、自転車の後ろに「〇〇インチ」と記されており、自転車の車輪(ホイール)のサイズはインチという単位で示しています。
子どもの成長に応じて、適切なサイズの自転車を選ぶことが大切です。
現在展開されているサイズは以下の通りです。ただし、メーカーによってサイズ感が異なるので、購入するメーカーの適正身長を参考にしてください。
12インチ 年齢:2~4歳 適正身長:85~105cm
14インチ 年齢:3~5歳 適正身長:92~107cm
16インチ 年齢:3~6歳 適正身長:98~119cm
18インチ 年齢:4~8歳 適正身長:103~125cm
子ども用自転車のサイズは2歳から8歳が対象年齢となっています。2歳から乗れるほどサイズ展開は豊富です。
購入する際はサドルを一番低く下げた状態で、子どもが自転車にまたがったときに、足のつま先がつくのが、適正なサイズの目安になります。
足の裏がつく高さだと、成長によって窮屈になりやすく、足が地面につかない高さだとバランスを崩した際、からだを支えられず危険だからです。
子ども用自転車の安全性
安全基準の目安として、BAAマーク・JISマーク認証付きの自転車を選びましょう。
BAAマークとは一般社団法人自転車協会が定めた安全基準をクリアした自転車に付与できるマークのことです。
JISマークを基準に作られた規格で、安全面を考えた自転車であるといえます。
ブレーキについては、子どもは大人より握る力が弱いため、慎重に選ばなくてはなりません。
試乗する際、子どもにブレーキを握らせてみて握りやすさをチェックするようにしましょう。
子どもが好きなデザイン
サイズが適正で安全性の高い自転車であっても、デザインが気に入らなければ乗り続けてもらえません。
子どもが気に入ったキャラクターやカラーを選ぶといいでしょう。
自転車の練習方法

補助輪なしで自転車の練習をする場合、バランス感覚を掴むことからスタートしましょう。
ストライダーのようにペダルなしのキックバイクまたがって、地面を蹴って進みます。最初は片足ずつで、できるようになったら両足で。
5秒程度進めるようになったら、ハンドルを切って曲がる練習もしてみます。同時にブレーキを握って止まる練習もしておきましょう。
キックバイクに乗り慣れていると足で止めようとするためです。
バランスが取れるようになったらペダルでこぐ練習を始めます。
自転車を後ろで支えてあげながら、ゆっくりペダルをこいでみましょう。上手くいかない場合はムリせず補助輪を使って練習するのもおすすめです。
ペダルがこげるようになったらもうすぐです。公道を実際に走ってみて、きちんとバランスが取れているか、ブレーキを正確にかけて止まれるかなど練習します。
最初はまっすぐ走れる練習し、できるようになったら運転の練習をしましょう。
自転車のルールとマナー
子どもが自転車に乗れるようになったら、必ず自転車の交通ルールを教えてあげてください。子どもの行動範囲が広がることは喜ばしいですが、その分事故の危険性が伴います。
交通ルールを知らずに運転すると、事故で命を危険にさらす可能性だけではなく、誰かを傷つけるリスクも高めてしまいます。
自転車は道路交通法上では軽車両として分類される車の仲間です。子ども自身や周囲の人たちが安全でいられるように警察庁がまとめた自転車安全利用五原則を守りましょう。
自転車は車道が原則
自転車は車の仲間なので車道と歩道がある道路では、車道を走るのが原則です。
車道走行だと自動車と同じ道路を走るのに危険を感じるかもしれませんが、自転車がよく見えるからこそかえって安全だったりします。
ただし、車道走行の原則は以下の例外があります。
道路標識・標示によって自転車の通行が可能とされている歩道を通る場合
運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、からだの不自由な人
車道や交通の状況からやむをえない場合(道路工事や路上駐車によって車道の左側通れないなど)
こうしたケースだと車道を自転車で走るのは危険となるため、歩道の通行が許可されます。
そのため、13歳未満の子どもには歩道を通行するよう伝えましょう。
車道は左側を通行
自転車で車道を走る場合、道路の左側によって通行しなくてはなりません。
自転車が左側を通行することで自動車から認識されやすくなります。
一方、道路の右側を自転車が通行する場合もありますが、あれは逆走です。
自動車に向かって走るため、運転手が判断を誤ると大変危険ですし、自転車にトラブルがあった場合車が反応できない可能性があります。
逆走については罰則が設けられていて、道路交通法第119条により、3か月以下の懲役か5万円以下の罰金に処される恐れも。
歩道のない道路で自転車が逆走する場面がよくみられるため、ルールだけではなく危険性についても教えてあげてください。

歩道は歩行者優先で車道寄りに徐行して走る
13歳未満の子どもは歩道を通行できますが、歩行者が優先されることを忘れてはいけません。徐行のスピードは時速10km以下ですぐに止まれる速さで走りましょう。
また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止が必要です。
子どもには人通りの多い場所では自転車を降りて押して歩くように伝えるといいでしょう。
二人乗りは違法
6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せる場合を除いて、自転車の二人乗りは禁止です。
道路交通法57条2項に基づき、各都道府県の公安委員会が定めた道路交通規則で原則違反とされています。
東京都の場合、自転車の二人乗りは2万円以下の科料に処せられる恐れがあるので覚えておきましょう。
もしも、自転車の二人乗りによって事故を起こしてしまうと、被害者であったとしても過失があるとして損害賠償金額が減額されます。
歩行者にケガをさせてしまった場合は、著しい過失として10%過失が重くなってしまうので、事故においても大きく不利になってしまうのです。
ながら運転
右手に飲み物、左手にスマホを持ち、イヤホンをしながら電動アシスト自転車を運転していた女子大生が77歳の女性を死亡させた事故がありました。
この事故に限らずスマホを操作しながら運転する「ながら運転」による事故により刑事罰で有罪、民事訴訟では高額の賠償を命じる判決がでています。
スマホ操作をしながら自転車を運転すると、各都道府県の交通規則に違反となり、5万円以下の罰金が科せられます。
ながら運転は軽い気持ちでやってしまうため、小さなうちから徹底したいものです。
夜間のライト点灯
夜間に自転車を通行するときは、前照灯と尾灯(または反射器材)をつけなくてはなりません。違反した場合は5万円以下の罰金が科せられます。
ただ、ライトをつけていればOKということではありません。都道府県によって多少異なりますが、ライトの明るさについて規約が存在します。
前照灯は白色か淡黄色、明るさは前方10メートル上にある交通上の障害物を確認できるといった内容です。
そのため、インターネット上で購入できる安物のライトだと条件を満たしていない可能性があります。使用しているライトが条件に適しているか確認しましょう。
ヘルメットの着用
自転車に乗るときはヘルメットを着用させるようにしましょう。警察庁では「保護者は13歳未満の子どもにヘルメットをかぶらせるよう努めなくてはなりません」としています。
警察庁の調べによると、自動車事故で死亡した方の約7割が頭部に致命傷を負っています。万が一の事故が起きてしまった場合、ダメージを最小限にするためにも、頭を守ることは大切です。
選び方としてはぴったりかぶれるサイズのものを選びましょう。実際に着用してサイズや形を確かめるのをおすすめします。
子ども用のヘルメットは軽くできていますが、実際かぶってみるとヘルメットの重みが気になる子が多いようです。サイズ感も大切ですが、あわせて重さも気にしてあげましょう。
子どもにヘルメットを着用させるのは保護者の努力義務です。罰則はありませんが、子どもの頭部を守るためにも必ずヘルメットは着用させましょう。
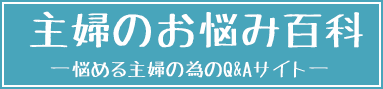


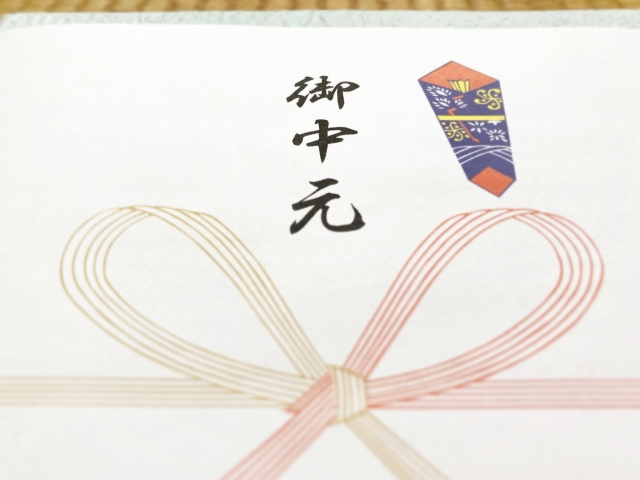 お中元の起源
お中元の起源  回覧板の回し方が分からない
回覧板の回し方が分からない  英会話勉強用にパソコンを購入しに行く
英会話勉強用にパソコンを購入しに行く  隣人に通行料を請求された
隣人に通行料を請求された  姑より小姑と相性が合わない
姑より小姑と相性が合わない